脳神経内科
- 5月12日(月)木村医師
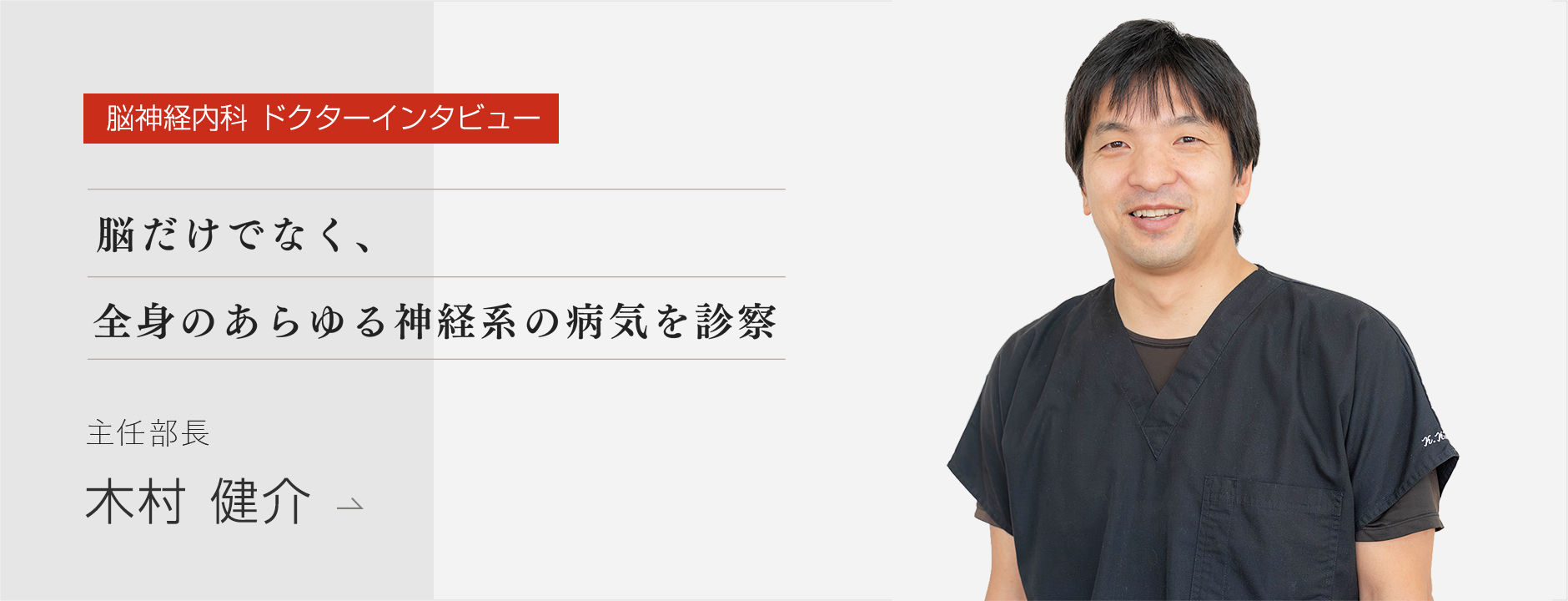
脳神経内科が担当する疾患は頭痛やめまい、脳血管障害、神経変性疾患、神経免疫疾患、神経感染症、てんかんなど多岐にわたり、日々の診療の中で脳神経内科医が必要とされる場面は数多くあります。
しかし、水戸市を含む茨城県の県央・県北地域は脳神経内科医が非常に少ない地域であり、特に神経変性疾患や神経免疫疾患など専門性が強く求められる疾患の診療を行う医師が不足しています。
上記の疾患のみならず、神経疾患には脳卒中やけいれん発作などの迅速な対応が求められるものがあります。例えば、発症から間もない脳梗塞は緊急でカテーテル治療の適応となることがあり、治療開始が早いほど良好な神経予後が得られることが分かっている時間が勝負の治療です。また、脳卒中以外にも痙攣発作や脳炎・髄膜炎といった疾患も、脳の損傷を防ぐために迅速な検査・治療が必要であり、時には人工呼吸器などを用いた集中治療が必要となることがあります。
当院はドクターヘリ、ドクターカーによる病院前診療も行う三次救急病院であるとともに、県央地域における中核病院です。当科としてはこれらの課題にこたえるため、下記を今後の方針として掲げています。
当院ではこれまで急性期脳梗塞に対する血栓回収療法は行っていませんでしたが、2023年10月から常勤の脳神経内科医が赴任したのに合わせて脳血管内治療を開始しました。2024年4月からはさらに脳血管内治療専門医の資格を持つ脳神経外科医が1名赴任したため、県央・県北地区における重症脳卒中患者を、24時間365日受け入れることが出来るようになりました。
多発性硬化症や重症筋無力症のような神経免疫疾患については、最近になって多数の生物学的製剤が治療薬として承認されており、ますます高い専門性が求められるようになりました。今後は神経免疫外来を立ち上げて、高い専門性を求められる神経免疫疾患の患者さんにも対応できるようにしていく予定です。
筋萎縮性側索硬化症や筋強直性ジストロフィーのような神経変性疾患は、現状では症状を改善させる治療はまだなく、最終的には介護が必要となる疾患です。神経変性疾患の患者さんに対しては地域の開業医や訪問診療医の先生方と連携しながら、患者さんにとって最も良い治療・ケアを提供できるようにしていく必要があります。当院も地域の中核病院としてそれぞれの地域と連携しながら、患者さんにとって最も適切な医療サービスを提供できるように努力していきます。
当院と隣接する茨城県立こども病院には、乳児期・小児期に発症した神経筋疾患の患者さんが多く通院されています。小児期に疾患を発症したお子さんが成長し成人になると、加齢による合併症、例えば生活習慣病や癌など成人疾患が診療上の問題となってくることがあります。また、成人になると医療体制、社会福祉体制も小児の枠組みから成人の枠組みに移行するため、成人後に該当する成人の診療科で診療を継続する必要が出てきます。
成人になると、医療体制の変化のみならず、自立が可能なお子さんの場合には、自立が出来るように支援が必要になります。それぞれの疾患・重症度に応じて疾患の理解促進や自己決定支援を行い、自立が難しい患者さんに対しても、やはり患者さんそれぞれの状態に応じた包括的な支援が必要です。
当科では隣接する県立こども病院とも連携しながら、移行期医療の対象となる患者さんの受け入れを行い、それぞれの患者さんに適した医療体制を再構築できるようにサポートしていきます。

当院では、脳の健康状態を総合的に評価するため、脳パフォーマンス(機能)チェックツール「のうKNOW」を導入しております。
